2007.07.01(2025.07.18 更新)
- 2007年
- 夏休み、セミのぬけがらをさがせ!
自然しらべ2007 夏休み、セミのぬけがらをさがせ!

調べる対象:セミ
自然しらべ2007「夏休み、セミのぬけがらをさがせ!」の結果概要がまとまりました。
参加者はのべ 19,871人・団体。集まったぬけがらは 20種、18,570個。
※実施時期:2007年7月1日~8月31日(終了)
自然しらべ2007「セミ」とは
セミのぬけがらは、その地域にそのセミがくらしている証拠。幼虫の間を土の中でくらすセミは、土地の環境変化をじかに受けるため、指標生物として知られています。また、セミのぬけがらを主に食べたり、すみかにしている生きものは今のところ見つかっていないため、採集による影響の少ない調査といわれています。
セミのぬけがらをテーマにした全国規模の市民参加型調査は、1995年に環境庁(当時)によって「第6回緑の国勢調査・身近な生き物調査」の一部として、また2001年にも同様に行われています。調査方法も確立されデータも残っているのですが、残念ながらその後は行われていません。そこで今度はNGOの力で最新の全国調査ができないかと考えました。
1995年から続けている自然しらべの今年のテーマは「セミのぬけがら」
セミは、幼虫時代の数年を土の中ですごします。遠くに行くことができないので、その土地の環境変化をじかに受けてしまいます。そのため、環境のバロメーターとして注目されています。
セミのぬけがらについては、市民参加の調査手法が研究されており、1995年と2001年には環境庁(当時)によって全国的な市民参加型調査が行なわれました。
セミのぬけがら調査は、地域ごとにはその後も活発に行われており、自然観察をしているNACS-J自然観察指導員のみなさんなどから、セミのようすが変わってきているのではないかという観察報告がよせられるようになりました。
植木などの根に幼虫がついて運ばれてきてしまったのか、地球温暖化やヒートアイランド現象などの影響なのか。人のくらしがセミに影響をおよぼしているのかもしれません。
全国的にセミのぬけがらをしらべてみることで、そんな変化を知ることができるのではないかと期待しています。

主催・協賛・協力
| 主催 |
|
|---|---|
| 協賛 |
|
| 誌面協賛 |
|
| 学術協力 |
|
| 指導 |
|
| 協力 |
|
| 写真提供 |
|
| ぬけがらイラスト |
|
| アシスタントスタッフ |
|




 主な活動 TOP
主な活動 TOP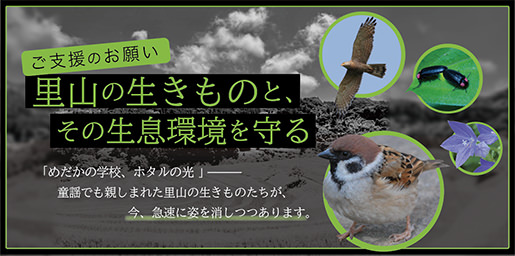
 支援の方法TOP
支援の方法TOP 会員制度/入会申込み
会員制度/入会申込み 遺贈・遺産・お香典のご寄付
遺贈・遺産・お香典のご寄付 チャリボン(本・DVD等での寄付)
チャリボン(本・DVD等での寄付) お宝エイド(不用品の買取寄付)
お宝エイド(不用品の買取寄付) 寄付金控除・褒章制度について
寄付金控除・褒章制度について その他の支援方法
その他の支援方法 講習会日程一覧・お申込み
講習会日程一覧・お申込み





