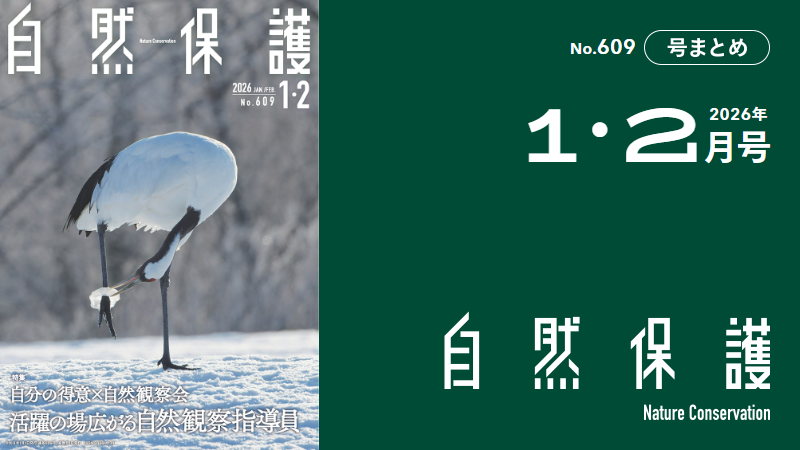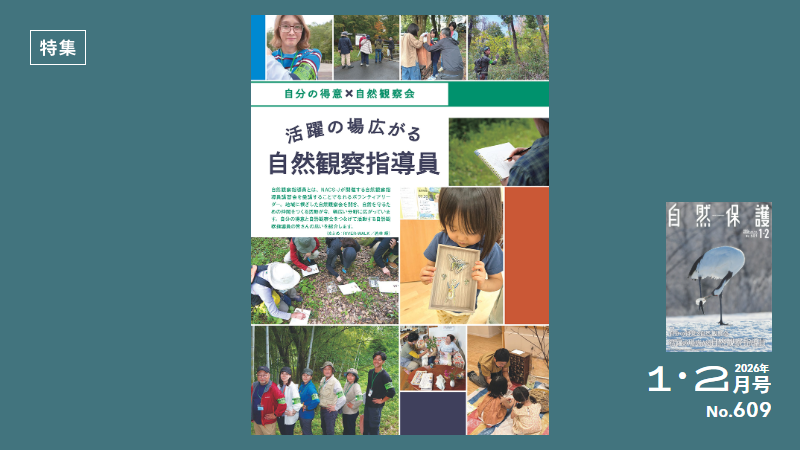N-Cafe 会員投稿コーナー
2025年9月1日

Contents
【募集】自然の中で“あるがまま”を見つめるORANGE JAMBOREE開催
千葉県
椎名淳一(自然観察指導員)
認知症ケアと自然観察を融合させた体験型イベント「ORANGE JAMBOREE~あるがままに~」を、11月8日(土)千葉県で開催します。
自然観察指導員でもある認知症介護指導者の案内のもと、自然との対話を通じて“共生”や“あるがまま”を見つめ直す時間を提供します。自然観察や講演、焚き火を囲むナイトセッションも実施予定です。自然と福祉の接点に関心のある方におすすめです。

【募集】写真展「サシバ・奄美の空を優雅に舞う!」を開催します
鹿児島県
与名正三(自然観察指導員)
本土で繁殖を終えたサシバは9月下旬、越冬のため奄美(鹿児島県)にやって来ます。成鳥は換羽を終えたばかり、幼鳥は生まれたばかりで、いずれも翼に欠損のない状態で飛翔する姿は優雅に見えます。
最近の研究でサシバは繁殖地である本土と越冬地に拠点を置き、本土では営巣地を拠点に、越冬地では縄張りを拠点に暮らしていることが分かってきました。本土での暮らしは繁殖が目的で、天敵からヒナを守るため警戒しながら生きていかなければなりません。人目を避け密かに暮らしているのです。対して奄美のサシバは越冬地に着いた直後から、毎年同じ場所で縄張りを構え、その上空を大な声で鳴きながら、ゆっくりと羽ばたき、縄張りを誇示します。奄美で開かれる国際サシバサミットの開催時期に合わせ、奄美空港で写真展を開催します。越冬地ならではの魅力あふれるサシバを探しに、奄美にぜひお越しください。

カンヒザクラを背景にウルシの横枝から飛び立つ成鳥
【報告】シンポジウム「長良川河口堰運用30年」を開催しました
愛知県
田中万寿(長良川市民学習会、NACS-J会員)
川と海を絶つ堰建設から30年。危惧していたように堰は自然環境と地域社会に大きな影響を及ぼしています。市民団体「よみがえれ長良川」(事務局・長良川市民学習会)は、7月6日に岐阜市で、これからの長良川河口堰運用を考えるシンポジウムを開催しました。
最初に主催者から長良川の現状と河口堰の歴史、韓国の洛東江(ナクトンガン)河口堰で進む開門について報告がありました。続いて4人のパネリスト〔宮本博司:当時の河口堰建設事務所長、蔵治光一郎:愛知県河口堰検討委員、森誠一:岐阜県河口堰検討委員、三石朱美:元国連生物多様性の10年市民ネットワーク〕が各々の経験に基づいて、「公共事業は地域住民のためのもの、結論を決めず真摯に住民の意見に耳を傾け対話すること」、「今こそ円卓会議を」、「対立を乗りこえて対話を」、「自然に謙虚に向き合いたい」などの意見を述べました。参加者のアンケートでは「事業者側の参加がなかったことは残念」、「原則を確認して対話を」、「かつての長良川を若い世代に」など多くの意見が寄せられました。私たちは住民を含めた関係者間の公平な対話を願って活動してきましたが、その門は開かれていません。
当日の動画は、長良川市民学習会のウェブサイトでご覧いただけます。

左から 亀井浩次氏(司会)、蔵治光一郎氏、三石朱美氏、森誠一氏、宮本博司氏
【募集】写真が語る山の自然「山岳環境データベース」にご協力ください
千葉県
下野綾子(日本山岳会自然保護委員、東邦大学理学部生物学科、NACS-J会員)
多くの高山地域では自然環境の変化の有無を判断する過去の科学的知見が不足しています。この不足を補える有力な記録は、過去に撮影された写真です。写真は調査記録を補う客観的な記録となり、過去と最近の写真の比較ができれば、植生の変化を検討することが可能となります。
そのため日本山岳会では、登山者が撮影した古い写真の収集を行ってきました。そして東北大学を代表とする研究プロジェクト「ネイチャーポジティブ発展社会実現拠点」の支援を受け、山岳環境の変化を見える化し共有する山岳写真データベースを作成しました。
当ウェブサイトで公開できる昔の写真を募集しています。デジタルカメラが普及する以前(1990年以前くらい)のもので、撮影日時の分かる春から秋の高山植生が映っているネガフィルム、ポジフィルム、プリント写真を対象としています。デジタル写真はウェブサイトから投稿できます。アナログデータの送付に関してはお問い合わせフォームからご連絡ください。
山のユーザーが写真を通じて山の環境をモニタリングし、その記録を共有し、山で起こっていることを知る、そんな仕組みづくりを目指しています。


南アルプス聖平(写真上:1987年8月4日 坂東明文氏撮影/写真下:2025年8月8日 道野仁氏撮影)
1987年当時は聖平小屋の赤い屋根がよく見えているが、現在は木が成長して見えなくなった。1959年の伊勢湾台風で多くの樹木が倒れ、それが回復しつつある途中である。またニホンジカの植生影響が深刻で、対策のため防鹿柵が設置されている。
イベント案内、活動報告、成果物紹介や、自然観察で撮影した面白い写真などの投稿を大募集!
あて先
〒104-0033 東京都中央区新川1-16-10 ミトヨビル2F NACS-J編集室
Eメール:kaiho2@nacsj.or.jp(送信の際は、@を半角にしてください)