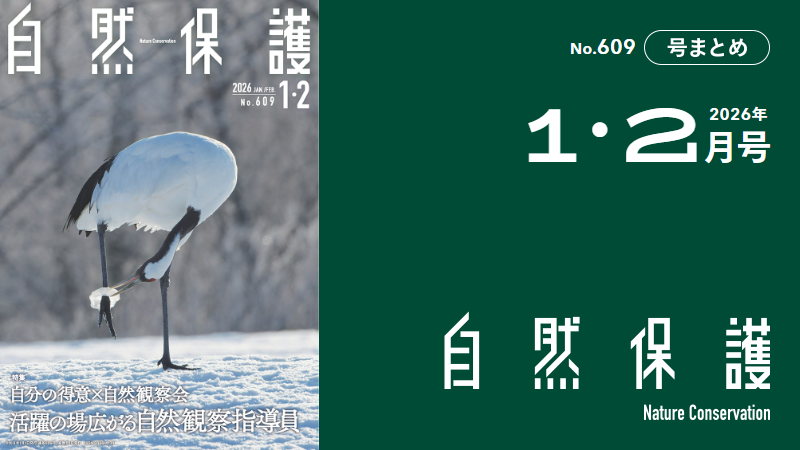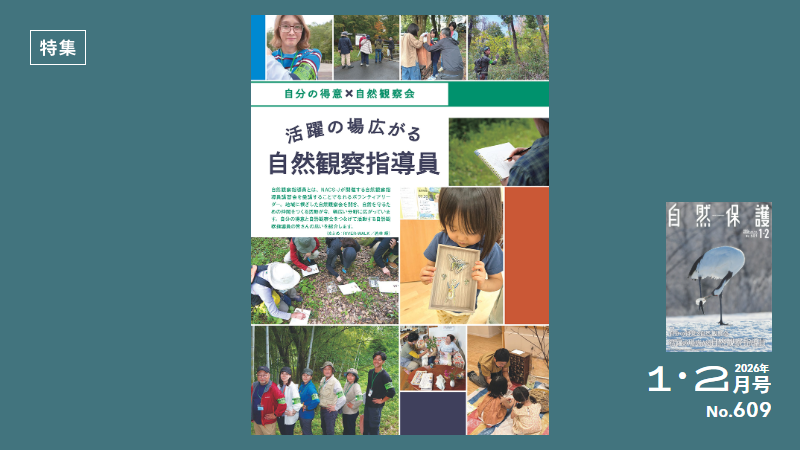【配布資料】今日から始める自然観察「ホバリングするハチに似た生きものは?」
2025年9月1日

このページは、筆者の方に教育用のコピー配布をご了解いただいております(商用利用不可・抜粋利用不可)。ダウンロードして、自然観察などでご活用ください。
花から花へ素早く飛び回る「ホウジャク」と呼ばれるガの仲間。ハチやハチドリに間違われることもある彼らの活発な行動は、身近な自然観察の対象として、とても魅力的な存在です。そんなホウジャクたちの暮らしに注目します。
矢崎英盛
東京都立大学理学部生命科学科特任助教
昼に活動するガの仲間

アベリアに訪花するオオスカシバ(写真:矢崎英盛)
花壇や公園で、空中で静止するように飛びながら(ホバリング)、蜜を吸って花から花へ、目にも止まらぬスピードで飛び回る生きものを見たことはありませんか?「ホウジャク」と呼ばれるガの仲間です。
ホウジャク類とよく呼ばれるのは、スズメガ(雀蛾)科の「ホウジャク(蜂雀)亜科」に含まれるガのうち、主に日中や朝夕の薄明るい時間帯に活動するものです。日本では19種が知られており、蜂雀の名の通りハチと間違えそうな姿と行動の持ち主ですが、毒はなく、人を刺すこともありません。
ホウジャク類はいずれの種も口吻がよく発達しています。高速で翅をはばたかせながら、普段は丸まっている口吻を伸ばして花の蜜を吸う様子は、その見事な飛翔能力を実感するチャンスです。観察のおすすめはアベリアの花壇。アベリアは都心部でもよく植栽されている低木で、春から秋まで私たちの目線より少し低いくらいの高さに白い可憐な花を咲かせ、そこにさまざまな種のホウジャク類が訪れる様子を楽しむことができるでしょう。
このホウジャク類とよく間違えられるものに、ハチドリ(蜂鳥)という鳥の仲間がいます。主に中南米に生息しているハチドリ類は(日本にはいません)、ホウジャク類と同じようにホバリングしながら花の蜜を次々に吸って飛び回ります。ホウジャク類とハチドリ類は、ガと鳥という全く違う生きものですが、このように異なる系統の生きものが同じような環境条件などで似た姿や行動などの特徴を持つことがあります。この現象を「収斂進化」と呼びます。ホウジャク類は、生きものが長い時間かけてたどってきた進化というシステムの面白さを、私たちに教えてくれる存在でもあるのです。
身近なホウジャクたち
オオスカシバ

都心でも見かけることの多いオオスカシバは、日中によく活動するホウジャク類では最も大きな種で、その名の通りの透明な翅が特徴です。(写真:矢崎英盛)
ホシホウジャク

身近によく見られる種の一つ。ホバリングしながらツリフネソウから吸蜜している。幼虫の食草はヘクソカズラ(写真:ピッキオ)
ホシヒメホウジャク

枯れ葉のような姿が印象的な種。成虫越冬と考えられており、早春にも見かける。幼虫の食草はヘクソカズラ(写真:矢崎英盛)
ヒメクロホウジャク

オオスカシバに似るが、より小さく翅が黒っぽい。幼虫の食草はアカネやヘクソカズラなど(写真:鈴木淳夫)
ホウジャク類の生活史
卵から生まれた幼虫は、大きくなると蛹になり、そこから翅の生えた成虫が羽化してきます(完全変態)。オオスカシバの幼虫の主な食べ物はクチナシの葉。しばしば公園や庭の植栽でも発生しているのを見つけることがあります。オオスカシバは一般に蛹で越冬するとされますが、ホウジャク類の一部の種では成虫で越冬すると考えられているものもいます。

食樹のクチナシの葉の上に、オオスカシバの緑色の丸い卵。柔らかい新芽で見かけることが多い(写真:PIXTA)

幼虫は体の後ろの端に「尾角」と呼ばれる突起を持つが、何のためなのかよく分かっていない(写真:鈴木淳夫)

幼虫は十分に成長すると、浅い地中または地表で蛹化する(写真:PIXTA)

羽化したばかりの成虫の翅には、黄色っぽい鱗粉が付いている。しかし翅を震わせるとこの鱗粉ははがれ落ち、透明な翅が現れる(写真:PIXTA)
これはホウジャク?

夜に飛ぶホウジャク亜科のガ
ホウジャク亜科には、夜に活動する種も多く含まれているが、一般に「ホウジャク」と呼ばれることは少ない。例えば写真のベニスズメは、夜に咲く花や樹液などの間を高速で飛び回り、やはりホバリングして口吻を伸ばしながら吸蜜する(写真:鈴木淳夫)

スカシバガ科は別のガ
オオスカシバとよく似た和名の「スカシバガ科」というガの仲間がいる(写真はセスジスカシバ)。こちらもハチにそっくりの姿だが、ホウジャク類とはかなり縁遠い別のグループ。特に飛んでいる時はブーンという羽音もあいまって、ハチと見分けるのが難しい(写真:矢崎英盛)
花とスズメガの関係

サギソウ(写真:photoAC)
観賞植物としても人気のサギソウのギザギザの花びらは、ホウジャク亜科を含むスズメガ科のガがホバリングしながら蜜を吸う際に、脚をかけて姿勢を安定させる支えとして機能する。つまりサギソウの花にとって、より確実に花粉を運んでもらう仕掛けになっている(Suetsugu et al. 2022)。
一方でスズメガ類は、ホバリングしながら花の雄しべや雌しべに触れずに蜜を吸い出してほとんど花粉媒介に寄与しない「蜜泥棒」としての側面も持っている(Sakamoto et al. 2012)。蜜を盗まれるのを避けるために、一部の植物は、スズメガ類の口吻よりも長い筒状の花を咲かせ、送粉者としてスズメガ類を利用している。スズメガ類と植物は、互いを搾取しようと戦いを繰り広げてもいるのである。(協力:阪上洸多)

本コーナーは、エプソン純正カートリッジ引取回収サービスを利用されたお客様のポイント寄付によるご支援をいただいております。