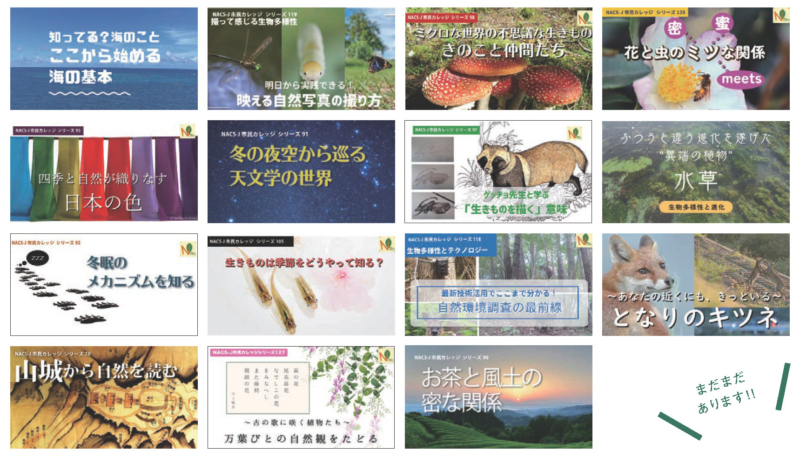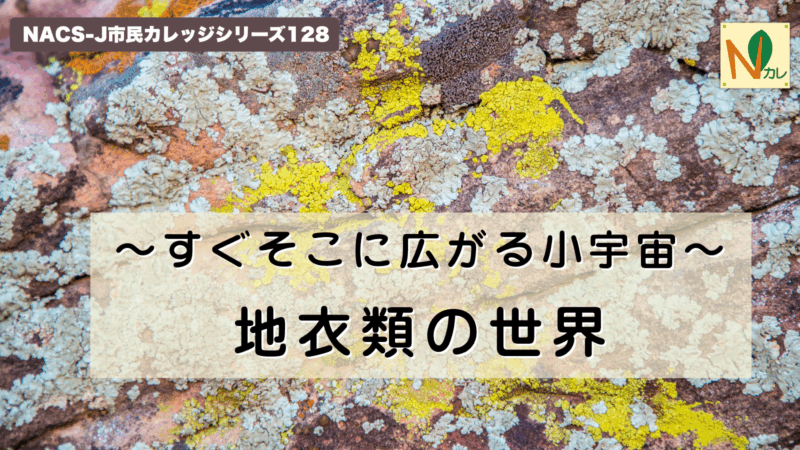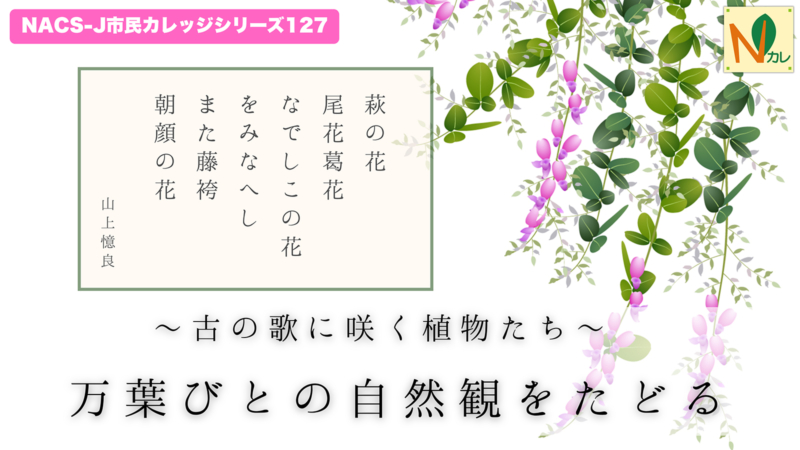NACS-J市民カレッジ119「撮って感じる生物多様性 明日から実践できる!映える自然写真の撮り方」を開催しました
2024年6月7日

日本自然保護協会(以下、NACS-J)は、一人でも多くの方に日本の自然の美しさや大切さ、尊さ、守ることの大切さを伝えたいという思いから、NACS-Jに集う各分野のスペシャリストが講師を務めるオープンカレッジ「NACS-J市民カレッジ」(以下、Nカレ)を開催しています。119回目のNカレは、「明日から実践できる!映える自然写真の撮り方」について学びました。
今回の講師は、昆虫・自然写真家の尾園暁さんです。尾園さんにお願いしたテーマは「映える自然写真の撮り方」。そこで尾園さんは、改めて「映える写真」というのはどういう写真なのかを考えてくださいました。
尾園さんが考える「映える」自然写真4つのポイント
- きれい
- かわいい
- 面白い
- インパクト
まずは、上記それぞれのポイントに沿って、尾園さんが撮影した昆虫写真の数々を、その生きものの生態や魅力の解説とともに説明してくださいました。
続いて、撮影するときに尾園さんが気をつけているポイントを学びました。
尾園さんが気をつけている7つのポイント
- 生きものの個性を活かす
- よく観察してから撮る
- 光を活かす
- 生きものへのストレスを考慮する
- 生息環境を壊さない
- ルール・マナーの遵守する
- 危険への対処
これらのポイントは、撮影のコツとしてだけでなく、尾園さんが生きものに悪影響を与えないように常に心掛けていることだそうです。こうした配慮があってこそ、生きものの魅力を最大限に引き出して表現できる写真が撮れるのですね。
撮影機材の話では、スマートフォン、コンパクトカメラ、一眼レフなど、それぞれのカメラの特長を生かした写真の撮り方を、尾園さんが実際に撮影した写真を例に紹介してくださいました。共通のテクニックとして、被写体に警戒されずに近づくアプローチが最も重要だそうです。
そして、最後に尾園さんが強調されていたことは、撮影して保存して終わりではなく、撮影後は撮った生きものの写真をぜひ自分で図鑑をみて調べてほしい、ということでした。そうすることで思いがけない発見があるかもしれないし、次は偶然ではなく狙った写真が撮れるようなるそうです。
「映えるがすべてではなく、生きものの撮影は、身近なところに埋もれた美しさや面白さを見つけては掬い上げる、宝探しのような作業。そうした撮影をしていると必然的に映える写真が撮れると思う。」という尾園さんの言葉がとても印象的でした。
質疑応答では、構図の考え方やよく使うレンズ、おすすめの虫よけ、腹ばいで撮影するときの服装はどんなものか、などさまざまな質問に対して、普段ではあまり聞くことのできない撮影秘話を教えてくれました。
参加者の声をいくつかご紹介します。
- 映える写真の考えが面白い。
- 写真がとても美しく、また機材や撮影時の様子、自然保護に関する内容まで、大変幅広く、面白いお話を聞くことができました。
- 観察することの大切さ、待つことで次のチャンスにつながるというお話がとても参考になりました。
- シャッタースピードの目安や昆虫への接し方、機材を柔軟に使用するなどの工夫について知ることが出来て良かった。
- 尊敬している写真家さんなのでどれもためになりました。特に「気を付けているところ」「機材」「いかに近づくか」と質問コーナーが参考になりました。
ご参加くださった皆さま、本当にありがとうございました。次回のNACS-J市民カレッジもお楽しみに。
アーカイブ動画は会員限定で公開していますので、ぜひご視聴ください。